渋谷区で主として中古マンションの売買仲介を行っている株式会社リアルプロ・ホールディングスの遠藤です。
日本に限らず世界各地の観光地でオーバーツーリズムが問題となっています。
日本では、京都や鎌倉の神社仏閣や個人邸などの立ち入り禁止エリアへの外国人の不法侵入、富士山の入山規制などにもかかわらず、弾丸登山を決行する外国人や、富士山周辺の忍野八海や富士河口湖町の「ローソン河口湖店」のインスタ映えスポットなど至る所で外国人のマナー違反の問題が噴出しています。
そもそもオーバーツーリズムという言葉は2015年頃にアメリカのネット系メディアが使いだしたのが始まりと言われています。
オーバーツーリズムは一言で言えば「観光公害」です。
特にインスタグラムやTikTokなどによる自己表現が、世界共通のスタンダードになった昨今では、観光地又は観光地では無いがインスタ映えするスポットとしてSNSで配信されたエリアに、大量の観光客が押し寄せることにより、そこに暮らす住民の生活に支障が出たり、そこを訪れる観光客自体がトイレが無かったり、楽しいはずの観光体験が混雑のため十分に味わうことが出来なかったりと、不快に感じてしまう状態をオーバーツーリズムと言います。
国連の世界観光機関ではオーバーツーリズムになる限界値として、物理的、経済的、社会文化的環境を破壊することなく、そして、観光客が許容できない程、満足度を低下させることなく、一か所の目的地を同時に訪れることができる最大人数としています。
ですから、例えあまり多くない観光客であっても、その村などのポテンシャルを超える人数(キャパシティオーバー)が訪れれば、必然的にそのエリアはオーバーツーリズムになってしまいます。
そして何より一番大きな問題のひとつがごみ問題です。
日本人は単一民族のため、ゴミをポイ捨てする人は少数ですが、外国人はそもそも文化が違うので平気でゴミを至るところに捨ててしまいます。
彼らの言い分としては、ゴミを清掃する仕事をしている人に仕事の機会を与えている、更には、「日本人のごみを捨てない行為は、彼らの仕事を奪っている」的な発想なので、そもそも論で話になりません。
「郷に入っては郷に従え」は英語では「When in Rome, do as the Rome do」と言う言葉があるように、世界共通言語だと思うのですが、現実は非常に厳しい状況です。
日本は更に公共のゴミ箱が非常に少ないにもかかわらず、観光地での食べ歩きはもはや旅行のひとつのイベントになっており、ゴミの捨て場がありません。
そのため、自販機脇に置いてある空き缶や空き瓶専用のごみ箱に食べかけの食べ物などを捨ててしまう人達が後を絶たないので、自販機脇のごみ箱も最近はめっきり減ってしまっており、まさに悪循環状態になっています。
政府は資源が乏しく、また地方の過疎化を防ぎ、外貨も稼ぐことができる観光を、これらの解決策の特効薬として「観光立国日本」を目指していますが、このオーバーツーリズムを解消しつつ、外貨を稼ぐためには、どのような対策を行っていけば良いのでしょうか。

入場規制や有料化、宿泊税の導入は必然
現段階でオーバーツーリズムを防ぐには、観光客を受け入れる設備や宿泊施設などをどんどん充実させていくという事はもちろん重要ですが、即効性のある手段としては「観光客がキャパシティーを超えないように人数を抑制させる」ことが何より重要です。
抑制手段として強い効力を示すのが、人数制限や完全予約制などとして、更に高い入場料を徴収するという方法です。
予約制とするだけで、時間的制約がかかるのを嫌い、その場所を訪れないと言う選択をすう観光客は多いと思います。
旅行では、自由な行動を取りたいと思う方は多く、時間制限をかけることにより、かなりの抑制効果が出ます。
更に入場料を高く設定することにより、本当にその場所を訪れたいと思う人達だけが訪れることになるので、マナー違反の減少も期待できます。
一方マイナス面としては、富裕層だけ優遇されてしまうという問題も浮上してしまいます。
トランプ大統領が関税をかけて大規模な規制をかけることによる不均衡と同じように、高すぎる入場料は格差という新たな弊害をもたらす可能性があります。
エリア全体に規制をかけるには、民間企業だけでなく、地方自治体の協力も必要になりますが、主として地方税と地方交付金を主な財源とする地方自治体の財政の運営はそこに暮らす住民に対しての財源であり、新たな観光対策用の費用の捻出は厳しいのが現状です。
そのため、現在地方自治体による宿泊税の導入や観光客の姫路城の入館料の大幅アップなどの入域料が盛んに検討されています。
以前ハワイを訪れた際に、現地の知人からロコは外国人よりも食料品などを安く買えるカードを持っていると言われたことがありますが、私も外国人と日本人(日本で暮らして税金を納めている外国人も含む)ではある程度格差をつけた方が良いと思います。
姫路城は現行は大人1,000円ですが、姫路市はこれを2,500円に値上げすると発表していますが、姫路市民は大人1,000円に据え置くとのことです。
6歳から18歳未満の小人は現行お300円を無料とするようですが、日本の城を代表する姫路城は日本人であれば姫路市民と同額の1,000円でも良いと思うのですが皆様はどうお考えになるでしょうか。
美術館や姫路城のように外部とのアクセスを制限できる門などがある場合には、入館料の徴収により、キャパシティーを超えない制限をすることは可能ですが、このような関所のようなものを設置できない場所の場合には、やはり、ある程度高額な宿泊税やそもそも日本を訪れる際の入出国税を大幅にあげる等を行う必要があるかもしれません。
海外では、観光客が多いバス路線を地図アプリに掲載しない、民泊の規制やまたは禁止、団体旅行の禁止、大型クルーズ船の乗り入れ禁止などを行っている、又は、検討している国や都市もあるようです。
鎌倉市では、今年のゴールデンウイークの5月3日~5月5日の12時~16時の間に沿線住民や沿線に通う学生や通勤者が、大混雑が予想される鎌倉駅構内に優先入場できる社会実験を行う予定です。
江ノ電は外国人観光客にも人気で、鎌倉駅の改札口や切符売り場付近はスペースが無く、あっという間に大渋滞が起き、人であふれかえってしまいます。
そのため、今年は4月23日から4月25日の期間中に江ノ電鎌倉駅構内や市役所で対象エリアに在住していることを証明できる書類等を持参し、申請すれば、改札を優先的に通過できるというものです。
尚、令和5年、令和6年に発行された証明書を所有している人は新たな申請は不要せ証明書はそのまま有効となります。
このような取り組みは今後ますます増えていくものと思われます。
一方で外国人旅行客の増加によるプラス面もあります。
日本を訪れる外国人旅行客は、平均で1週間程度滞在するので、日本人観光客と違い、外国人観光客が土日に集中する訳では無いので、外国人旅行客が増加すれば、安定した雇用環境や平日は閑古鳥が鳴くような施設の減少も予想され、プラス面は非常に大きいと言えます。
ちょっと難しい話になってしまいますが、先ほどお話しをさせて頂いた宿泊税については多くの自治体で既に導入または導入を検討していますが、観光客以外のビジネス客や地域住民が宿泊する際に「応益課税(地方自治体は行政サービスの提供を主な役割としており、地域に暮らす人々は何らかの形でその利益を得ているので、その受けた利益に応じた税負担を負うという考え)」として一律に徴収するのはおかしく、「原因者課税(来訪者がエリア内の財政需要(自治体に求められる行政サービスの質・量 )を 膨張させるので、その膨張による歳出増加を、原因者である来訪者に負担してもらうという考え)」が正論と言う意見も出ています。

オーバーツーリズムは物価と不動産の上昇を誘発する
オーバーツーリズムは、やっかいなことに物価の上昇や不動産価格の上昇も招きます。
日本を観光目的で訪れる外国人の多くはそれなりの生活水準を維持している人も多く、更に、観光で訪れているので財布のひもが緩みます。
デフレ状態が続いていた日本人相手では、安く提供しなければならなかったレストランやホテルは、値段を高くしてもどんどんくる外国人を標準として値段設定をあげていきます。
それを見た不動産オーナーは賃料をあげて利益を得ようとします。
この一連の動作により、物価も不動産も上昇していきます。
北海道のニセコの次は白馬周辺、そして今は築地をはじめ銀座や青山、渋谷などの都心部の飲食店やホテルの価格が高騰しています。
更に治安が良い日本で観光を満喫した富裕層が、外国人に対して規制の緩い日本の不動産を購入するため、ニセコや白馬、沖縄、都心部の不動産はどんどん価格が上昇しています。
こうなってしまうと、もはや日本人でこれらの人気エリアの不動産を購入できるのは上場企業の役員や会社経営者、一流スポーツ選手、お医者さんなど、ごくわずか人に限られてしまい、日本人の多くはその周辺地さえも購入が難しくなり、日本人の住むエリアのドーナツ化現象が起きることになります。
コロナ禍を経て、以前のような通勤ラッシュ程ではありませんが、最近は社員に出勤を要請する企業も増えており、満員電車に揺られて通勤通学することになり、更に、特別な日でないと都心部のオシャレなレストランや和食屋さんにも行けなくなってしまう可能性が現実化しつつあります。
旅行は誰もが楽しく、また異文化を体験できる貴重な機会をもたらす一方で、地域との摩擦や家賃の上昇、不動産価格の上昇による住民の締め出しや環境破壊、交通機関の渋滞、観光客を狙ったスリなどによる治安の悪化など、地域の住民にとって負の要因が増加するにもかかわらず、地域住民が観光客の増加に伴い恩恵を受ける機会は少なく、利益は観光業と観光客だけが得ることになり、この非対称性が諸悪の根源となっています。
先述したように資源が少なく、南北に長く四季が楽しめ、食の多様性と文化的価値が高い日本が外貨を稼ぎ、地方の過疎化を防ぐには観光は、なくてはならない日本の財産ですが、様々な問題点を抱えており、どのように進んでいくかは今後とも目が離せないと言えます。
いずれにしろ日本が観光立国として、成熟するには、規制の一本化だけではなく、それぞれの地域に沿った、規制強化や逆に規制緩和などを行っていく必要性があると思います。
『住まいんど診断』であなたの性格に合ったマイホーム探しを始めませんか!
無料で出来る自分自身の性格と住まい探しで重視するポイントがわかる住まい探しのための性格診断ツール
簡単2分で診断完了!ますは公式LINEから診断を!
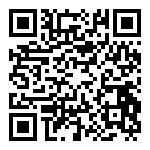





コメントをお書きください